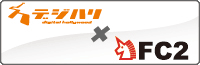彩―隠し事 438
変転-16
薄明りの中でヒクヒクする窄まりに指を伸ばすことなく、息を吹きかけたばかりの髪の生え際に乾いた舌を伸ばしてなぞる。
「ウッ、イヤァ~ン、ゾクゾクする……」
無言の健志は首筋から背骨の左側に舌を這わせて腰まで撫で下り、右手は少し遅れて背骨の右側を擦る。
舌と右手は休むことなく腰から首に向けて産毛を逆立てるように繊細なタッチで刺激する。
「ウッウッ、イヤァ~ン、焦らされているような感じがいぃの。気持ちいぃ」
「可愛いよ、オレだけの優子。離さないよ」
離さないという言葉と共に優子の左手を包み込む手に力を込める。
「離さないでね。健志は私のことをウサギちゃんだって言ったでしょう??」
「言ったよ。ウサギは性欲が強いし、寂しいと死んじゃうらしい……後者は嘘と言うか、間違いらしいけどね。優子を寂しいと感じさせないと約束する……これからは私と言うんだね??」
「うん、これからは健志のことを考えるのに世間体を気にせずにすむでしょう。自然体で付き合えるんだもん」
優子の左手を包み込むように握ったまま頬に唇を合わせると、
「イヤッ、キスはお口でしょう??」
「クククッ、優子の太陽はキスだったようだね」
「違うよ、分からないの??私にとっての太陽は健志。健志のそばにいるだけで、身体も心もほっこり満足する……嬉しい??」
頑なに俯せの姿勢を崩さなかった優子は自らの、太陽は健志という言葉に触発されて仰向けになり恥ずかしそうに目を閉じる。
糸くず一本纏わず、健志を魅了してやまない艶めかしい裸体を晒す優子は離婚を契機に身体だけではなく心の奥の隠し事も開放する悦びに打ち震える
自然と震えを帯びる羞恥で目を閉じたまま右手を股間に、左手で胸の膨らみを隠そうとする。
「可愛いなぁ。これからは誰に憚ることなく大好きだ、オレの女だと言ってもいいんだろう??」
「クククッ、私が健志のことを認めればね……エッチなウサギちゃんだから満足させてくれないと嫌いになっちゃうかも……ウフフッ」
「優子に嫌われないようにしなきゃいけないな……」
愛していると言っていた夫との悲しい別れを忘れさせようとするかのように健志は愛する気持ちを伝えようとする。
「気を遣わなくていいよ…あの人のことを愛していたのは事実だけど、健志の方がもっともっと好きだった。知っていたでしょう??」
「分かった、これからは他人を気にせずに二人の生活を考えよう」
右手で左乳房を包み込み、手の平に吸い付くような感触に頬を緩める健志が顔を近付けると優子は静かに目を閉じる。
ツンツン、二人の唇が欲望を高めるためにつつき合い、這い出た舌が妖しく絡み合う。
ウッウッ、ハァハァッ……欲情の昂ぶりは限界を迎え、ヌチャヌチャと卑猥な音を立てて舌が絡み合い、互いの唇をこじ開けるようにして出入りを繰り返して唾液を啜り合う。
左乳房を揉む右手の動きが激しくなり、右足が優子の両脚の間に入り込んで太腿が股間を刺激する。
「ウグッ、クゥッ~、たまんない。いぃ、いぃの……身体の芯が熱くなる」
「すごいよ、優子。優子の肌に吸い寄せられるような気がする…下腹部や腿がねっとり絡みつくようで気持ちいいよ」
左胸を揉まれ、こじ入れた太腿で股間を愛撫される優子はめくるめく悦びに酔い痴れ、顔を仰け反るようにして白い喉を見せ、乾いた唇に舌を這わせて滑りを与える。
そんな優子を見つめる健志は、探し続けていた大切なモノを手にしたような悦びで閉じたままの瞼にチュッと舌を合わせる。
「ウフフッ、大切にされていると思うけど本気で愛してほしい。健志の女だと宣言するように愛されたい」
右手は左胸を揉みしだき、伸ばした舌で右胸の先端をつつき、右脚は股間を圧迫したり緩めたりを繰り返しながら擦りあげる。
「アンッ、イヤッ……私は健志の女だよね。そうだと言って……」
「優子ほど大切な人はいない。オレから離れることは許さないよ……」
囁くような言葉が終わると胸に添えられた右手が頬を擦り、それが合図のように優子は目を閉じて唇を尖らせる。
「可愛いよ、オレの優子……」
唇を合わせると二人の舌は貪欲に互いを貪り、唾液を啜り息の続く限り舌を絡み合わせる。
甘噛みして上顎を舐め、苦しくなるとハァハァッと荒い息を漏らして離れ、赤く燃える瞳で見つめ合う。
優しくされるよりも荒々しく抱かれて悲しい事実を忘れたいと思っていた優子は、北風と太陽の寓話のように温かい愛に包まれて心の奥で冷たく固く凍っていた嫌な思いが氷解していくのを感じて健志の胸に顔を埋める。
「優子、無理をしなくてもいいんだよ。疲れた時は休むもよし、歩くペースやコースを変えて気分転換するもよし、手を伸ばせば届く距離にオレがいることを忘れないでくれ……笑っている優子のそばにいることがオレの幸せなんだからね」
「優しい言葉を聞かされると泣いちゃうよ。泣いている私のそばにいるのも幸せなの??」
「クククッ、可愛いなぁ。悪いけど今日が一番幸せな日かもしれない……明日からは、もっともっと、幸せな日が続くと思うけどね」
「健志は私を泣かせようとしているでしょう??昨日は、これまでの人生で一番不幸な日だと思ったけど、今日は健志に会ったとたん一番幸せな日になっちゃった。北風よりも太陽が好き……ねぇ、入れて。気もち悪いほどドッロドロになっているんだもん」
言葉を発すことなく口元を緩めた健志は自らの分身を摘まみ、優子の股間に擦り付けて十分に馴染ませ、腰を突き出すと、ジュルジュルと卑猥な滑り音と共に分身は泥濘に没していく。
「ウッウッ、クゥッ~…くる、くるっ、アァ~ン、気持ちいぃ……ダメッ、動いちゃダメ。このまま……アァ~、このまま健志を感じていたい……」
「優子、好いよ、気持ちいぃ。他人を気にすることなく、彩じゃなく優子と呼べる日が来ると思っていなかった」
薄明りの中でヒクヒクする窄まりに指を伸ばすことなく、息を吹きかけたばかりの髪の生え際に乾いた舌を伸ばしてなぞる。
「ウッ、イヤァ~ン、ゾクゾクする……」
無言の健志は首筋から背骨の左側に舌を這わせて腰まで撫で下り、右手は少し遅れて背骨の右側を擦る。
舌と右手は休むことなく腰から首に向けて産毛を逆立てるように繊細なタッチで刺激する。
「ウッウッ、イヤァ~ン、焦らされているような感じがいぃの。気持ちいぃ」
「可愛いよ、オレだけの優子。離さないよ」
離さないという言葉と共に優子の左手を包み込む手に力を込める。
「離さないでね。健志は私のことをウサギちゃんだって言ったでしょう??」
「言ったよ。ウサギは性欲が強いし、寂しいと死んじゃうらしい……後者は嘘と言うか、間違いらしいけどね。優子を寂しいと感じさせないと約束する……これからは私と言うんだね??」
「うん、これからは健志のことを考えるのに世間体を気にせずにすむでしょう。自然体で付き合えるんだもん」
優子の左手を包み込むように握ったまま頬に唇を合わせると、
「イヤッ、キスはお口でしょう??」
「クククッ、優子の太陽はキスだったようだね」
「違うよ、分からないの??私にとっての太陽は健志。健志のそばにいるだけで、身体も心もほっこり満足する……嬉しい??」
頑なに俯せの姿勢を崩さなかった優子は自らの、太陽は健志という言葉に触発されて仰向けになり恥ずかしそうに目を閉じる。
糸くず一本纏わず、健志を魅了してやまない艶めかしい裸体を晒す優子は離婚を契機に身体だけではなく心の奥の隠し事も開放する悦びに打ち震える
自然と震えを帯びる羞恥で目を閉じたまま右手を股間に、左手で胸の膨らみを隠そうとする。
「可愛いなぁ。これからは誰に憚ることなく大好きだ、オレの女だと言ってもいいんだろう??」
「クククッ、私が健志のことを認めればね……エッチなウサギちゃんだから満足させてくれないと嫌いになっちゃうかも……ウフフッ」
「優子に嫌われないようにしなきゃいけないな……」
愛していると言っていた夫との悲しい別れを忘れさせようとするかのように健志は愛する気持ちを伝えようとする。
「気を遣わなくていいよ…あの人のことを愛していたのは事実だけど、健志の方がもっともっと好きだった。知っていたでしょう??」
「分かった、これからは他人を気にせずに二人の生活を考えよう」
右手で左乳房を包み込み、手の平に吸い付くような感触に頬を緩める健志が顔を近付けると優子は静かに目を閉じる。
ツンツン、二人の唇が欲望を高めるためにつつき合い、這い出た舌が妖しく絡み合う。
ウッウッ、ハァハァッ……欲情の昂ぶりは限界を迎え、ヌチャヌチャと卑猥な音を立てて舌が絡み合い、互いの唇をこじ開けるようにして出入りを繰り返して唾液を啜り合う。
左乳房を揉む右手の動きが激しくなり、右足が優子の両脚の間に入り込んで太腿が股間を刺激する。
「ウグッ、クゥッ~、たまんない。いぃ、いぃの……身体の芯が熱くなる」
「すごいよ、優子。優子の肌に吸い寄せられるような気がする…下腹部や腿がねっとり絡みつくようで気持ちいいよ」
左胸を揉まれ、こじ入れた太腿で股間を愛撫される優子はめくるめく悦びに酔い痴れ、顔を仰け反るようにして白い喉を見せ、乾いた唇に舌を這わせて滑りを与える。
そんな優子を見つめる健志は、探し続けていた大切なモノを手にしたような悦びで閉じたままの瞼にチュッと舌を合わせる。
「ウフフッ、大切にされていると思うけど本気で愛してほしい。健志の女だと宣言するように愛されたい」
右手は左胸を揉みしだき、伸ばした舌で右胸の先端をつつき、右脚は股間を圧迫したり緩めたりを繰り返しながら擦りあげる。
「アンッ、イヤッ……私は健志の女だよね。そうだと言って……」
「優子ほど大切な人はいない。オレから離れることは許さないよ……」
囁くような言葉が終わると胸に添えられた右手が頬を擦り、それが合図のように優子は目を閉じて唇を尖らせる。
「可愛いよ、オレの優子……」
唇を合わせると二人の舌は貪欲に互いを貪り、唾液を啜り息の続く限り舌を絡み合わせる。
甘噛みして上顎を舐め、苦しくなるとハァハァッと荒い息を漏らして離れ、赤く燃える瞳で見つめ合う。
優しくされるよりも荒々しく抱かれて悲しい事実を忘れたいと思っていた優子は、北風と太陽の寓話のように温かい愛に包まれて心の奥で冷たく固く凍っていた嫌な思いが氷解していくのを感じて健志の胸に顔を埋める。
「優子、無理をしなくてもいいんだよ。疲れた時は休むもよし、歩くペースやコースを変えて気分転換するもよし、手を伸ばせば届く距離にオレがいることを忘れないでくれ……笑っている優子のそばにいることがオレの幸せなんだからね」
「優しい言葉を聞かされると泣いちゃうよ。泣いている私のそばにいるのも幸せなの??」
「クククッ、可愛いなぁ。悪いけど今日が一番幸せな日かもしれない……明日からは、もっともっと、幸せな日が続くと思うけどね」
「健志は私を泣かせようとしているでしょう??昨日は、これまでの人生で一番不幸な日だと思ったけど、今日は健志に会ったとたん一番幸せな日になっちゃった。北風よりも太陽が好き……ねぇ、入れて。気もち悪いほどドッロドロになっているんだもん」
言葉を発すことなく口元を緩めた健志は自らの分身を摘まみ、優子の股間に擦り付けて十分に馴染ませ、腰を突き出すと、ジュルジュルと卑猥な滑り音と共に分身は泥濘に没していく。
「ウッウッ、クゥッ~…くる、くるっ、アァ~ン、気持ちいぃ……ダメッ、動いちゃダメ。このまま……アァ~、このまま健志を感じていたい……」
「優子、好いよ、気持ちいぃ。他人を気にすることなく、彩じゃなく優子と呼べる日が来ると思っていなかった」