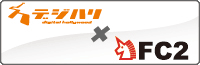期待 -2
チンッ……エレベーターが一階に着いてドアが開く。
「一階に着いたよ、今からどうするの??二時間くらいは大丈夫って言ったよね」
「ラブホで久しぶりに彩の白い肌を舐め回そうかと思ったけど今日は止めとく。オレが彩に求めるのはムッチリとした白い肌だけじゃないって知って欲しいからな。勿論、エロイこの身体は欲しいよ、でも今日は我慢する」
「ふ~ん、遊んでほしい気もするけど嬉しいかも……ウフフッ、彩の身体だけじゃなく心も欲しいと思っている??」
「そうだなぁ、本音は隠しといて、彩の心を欲しいとは言わない。彩にはご主人がいる、心はアッチ、身体はコッチが長く関係を続ける条件だろう」
浮気をしている亭主に心を許す気はないけど、今はそんな会話をする場面じゃないと自分に言い聞かせる。
「本音は隠したって言ってくれたから嬉しい……えっ、こんなに人がいるって気付いていた??」
「見られているし、すべてじゃないけど聞かれていたよ。ここにいる人たちに、彩にはご主人がいるのにセックスに飢えた悪い人妻だって知られちゃったね」
「いやっ、ねぇ、早く行こうよ。どこでもいいから連れてって、恥ずかしい」
エレベーターを降りた時には誰もいなかったので安心した彩は壁に背中を預けて小柄な身体を健志の胸に埋め、久しぶりに吸い込む匂いと逞しい男の感触に酔いしれて卑猥な会話を楽しんでいた。
ふと顔を上げた拍子に見えた健志の向こうには、いなかったはずの人たちが興味深げに二人を見ている。
「この人には亭主がいるけど、その亭主よりもオレの方がこの人を好きだ……不倫は好いか悪いか分かんないけど、浮気はダメだ。オレはいつも本気。浮ついた気持ちじゃなく亭主のいるこの人を本気で好きなんだよ。あんたらも幸せにな……騒がせたな」
ワインを二杯ほど飲んだだけで酔っぱらっているはずのない健志が長広舌をふるい、久しぶりに会った彩を前に本音をぶちまける。
「行こう、走ろうよ」
武志の手を握って通りへ出た彩は長い夜を楽しもうとする人たちの間を縫うようにして走り、健志は笑顔で後を追う。
「ハァハァッ……びっくりした。あんなことを急に大声で叫ぶなんて、ハァハァッ、気が触れたかと思っちゃうよ。久しぶりに走ったけど気持ちいい」
「彩を驚かせようとしたんだから目的は達成できた。クククッ、でも嘘は言ってないよ……着いたよ、この店に入ろう」
BARと書かれた木の扉を引くとカウンターとバックバーが目に入り、バーテンダーが、いらっしゃいませの言葉で迎えてくれる。
視線を巡らすと窓を背にしてゆったりとしたテーブル席があり、食事を楽しむカップルもいる。
「入口の扉には、BARの表示があったよね。バックバーも充実しているけど食事も美味しそう」
「特に自家製の燻製が美味いよ……席に着こう、変な人たちと思われちゃうよ。テーブルとカウンター、どっちがいい??」
「今日の健志は十分に変だもんね……テーブル席が好いな」
「いらっしゃいませ。今日はきれいな方とご一緒で輝いていますよ」
「あれっ、いつもと違って随分と軽口をたたくね」
「この間のカクテルコンペテションで金賞を頂いたんです。こちらの女性に幸運のおすそ分けです」
「えっ、事情がよく呑み込めないけど、ありがとうございます」
「今日はテーブル席にするよ……彩、この店のバーテンダーは皆、腕に自信のある人たちだよ……食事を済ませてきたから、ピーチツリーフィズとジントニック、ピクルスとオリーブ。燻製はお任せでお願いします。フィラージュは二杯目で頂きます」
「ねぇ、今の女性バーテンダーさんはすごいの??」
「カクテルコンペで何年も連続で金賞を取っている人だよ。二杯目に今年のオリジナルカクテルを飲もう」
チーズや砂肝の燻製は美味く、冷えたカクテルが身体中に染みわたる。
「美味しい。ピーチツリーフィズの甘い桃の香りとスモークの香りがよく合う。
ピクルスやオリーブも美味しい。この店の食事を食べたいけどフォンデュでお腹がいっぱい、残念だな」
「次の機会には必ず、約束する」
淡い色と甘酸っぱいオリジナルカクテルを堪能した彩は満足の笑みを浮かべる。
「一つ聞いてもいい??」
「どんなこと??」
「エレベーターを降りた時に叫んだこと」
「なにを言ったっけ、憶えてないよ」
「オレはこの人が好きだ。浮ついた気持ちじゃなく、本気で好きだって言ったでしょう……ねぇ、どうなの??彩を好きって本当なの??……本当の名前も知らないのに」
「名前なんかどうでもいい。目の前の彩は触れることも抱くことも出来る。それが事実だよ」
「ウフフッ、信じる。彩も健志が好き、大切な人だよ」
店を出て駅に向かうには目の前にあるペデストリアンデッキに上がればいいのに健志は彩の手を引いて路地に入る。
速足で歩く健志に合わせる小柄な彩は小走りになり、飲んだばかりのカクテルのせいもあって握られた手の平が汗ばんでくる。
目の前にラブホらしい看板が見えると健志の歩みは落ち着き、彩の心臓は口から飛び出さんばかりに早鐘を打つ。
私には主人がいるの、今日は帰らなきゃいけないのと言おうとした瞬間、狭い横道に引き入れられる。
数メートル歩けば行き止まりになるこの場所は他の誰も入ってくる可能性はなく、木の陰で隠れるようにして壁に押し付けられ、唇を合わせられると抗うことなく背中に手を回してしがみつく。
アルコールの匂いをさせてキスされると、これはジンの匂いなのかなぁと彩自身が何を考えているのかと不思議な気持ちになる。
息を荒げる健志は彩が着るブラウスのボタンを引き千切るように外し、ノーブラの乳房を剥き出しにする。
路地のそのまた奥の場所には街路灯の灯りが届かず、薄暗い中で妖艶な姿を晒す白い乳房を鷲掴みして先端にむしゃぶりつく。
スカートを捲り上げられて泥濘に指が伸びると、ヒィッ~と悲鳴にも似た喘ぎ声を漏らして、
「ダメッ、もうダメ、我慢できない。入れて、健志のオチンポで彩を気持ち善くして……はやく、おねがい」
右手で彩の左足を抱え上げて押し付けたペニスを馴染ませ、
「入れるよ……ウッ、温かくて気持ちいい。ごめんな、彩。我慢できなかった」
「アウッ、クゥッ~……いいの、これが欲しかったの、つながりたい気持ちを紛らすために仕事を一生懸命してたの。イィッ~、気持ちいぃ……」
ヌチャヌチャッ、ニュルニュルッ……健志は彩の左足を抱えて股間を突き上げ、彩は喘ぎ声を漏らすまいとして手の甲を口に押し付ける。
期待 -1
優子の提案で始まった新規プロジェクトは順調に進み、プロジェクトリーダーとして過分とも思えるほどに評価されて順風満帆に思えるし当初からのメンバーである栞と松本の表情も明るく覇気に満ちているようで、先行きに何の懸念も感じていないことが不安にさせる。
治に居て乱を忘れずという孔子の言葉を自らに言い聞かせる。
夫の浮気は相変わらず続いているようで休日は何かと言い訳して出かけるし、休日を挟んだ出張の際にはこれまでになかったようなお土産を買ってきてくれる。
浮気相手を呼んで出張先でのデートを楽しむ後ろめたさだろうと思うが、以前ほどに気持ちが騒めくことはなく、むしろ次の出張はいつだろうと期待さえしてしまう。
恋愛と言うより性的に奔放な栞に誘われたSMショーパブを通じて知り合った健志の存在のお陰だと思う。
元々、不道徳な事を許せない優子であったが、彩という架空の女性になって健志との逢瀬を楽しんでいる。健志とのセックスでは心の奥の秘密箱に隠していたSM遊びや露出癖が姿を現し、優子から彩に変身して楽しんでいる。
不貞と言う夫に対する隠し事を持つことが夫への怒りを半減して精神的均衡を保つのに役立っていると自分に言い訳をする。
その健志とは仕事が忙しい事もあってしばらく会えずにいたが今日は夫が残業で遅くなり食事も必要ないと連絡があったので、夕食を共にする約束を取り付けた。
「優子、夕食に行かない??忙しかった仕事も一段落したし久しぶりに二人で食事したいと思わない??」
学生時代からの付き合いで甘え上手な栞の言葉に心惹かれながらも、
「今日は用があるからダメなの、ごめんね」
「そうなんだ、でも何か怪しいな……まさか浮気してないよね??優子は私と違うから、そんな事はないか」
「そうだよ、私は栞と違って身持ちが固いの、好いなと思う男性がいても浮気はしません」
栞が退社するのを確かめた優子は化粧室でパンツをスカートに着替えてブラジャーを外し、健志に会うための彩に変身する。
彩の帰宅に便利なように決めた待ち合わせ場所に向かう途中、同僚など見知った顔がない事を確かめて用心し最寄り駅で下車してカフェに向かう。
待ち合わせのカフェで彩を迎える健志は立ちあがり満面の笑みで迎えてくれる。
「久しぶり、忙しそうだね」
「お久しぶりです。健志さんを忘れるくらい忙しかったのは事実」
「えっ、健志さんって言った??忘れられて他人になっちゃったようだね、最後の食事は何にしようか??」
「いじわる、彩の事が嫌いになったの??」
「嫌いになるはずがないけど、別れを告げられるのかと覚悟したよ」
「そんな事を言われたら、これから冗談も言えない」
「ごめん、そんな積りはなかったけど、今日こそ連絡があるかと待つ日が続いたから過敏になっていた。ほんとにゴメン」
「ふ~ん、そうなんだ。それを聞いて少し嬉しいかも……ウフフッ、後でご褒美を上げる。その前に腹減った。肉を食いたい、肉を食わせろ」
わざとらしく蓮っ葉に振舞う彩を愛おしく思う健志は周囲の看板に目をやり、あの店にしようと指差す。
健志の指したスイス料理店が入るビルのエレベーターに乗ると彩は早速、痴情をあからさまにする。
「クククッ、彩に会えなくて寂しかった??ねぇ、寂しかったの??」
「残念だけど、そんな事はないよ。寂しいはずがない……彩に会えない日々は頭ン中で好きに苛めることが出来るし妄想を膨らませて嬲り放題さ。クククッ」
「いやらしい……健志に苛められる彩はノーブラだった??」
仕事帰りの彩はスカートスーツのブラウスのボタンを外して白い胸の膨らみを健志に見せつける」
「えっ、彩はノーブラで仕事をしているの??色恋で仕事をしているんじゃないだろうな??」
「フフフッ、妬ける??しないわよ。久しぶりに健志に会うから外してきたの、仕事中はパンツだったんだけどスカートに着替えてきたんだよ」
「それじゃぁ、下もお土産を用意してくれたかなぁ……おっ、ノーパンだ。パイパンマンコだったのが薄っすらと髭を生やしているね」
「今日は時間がなくて無理だけど、今度会うときは健志にショリショリしてもらおうかなと思って……いや??」
「おい、よせよ。そんな事を聞かされると歩けなくなっちゃう」
「えっ、どうして??……まさか……ウフフッ、セックスを覚えたばかりの少年みたいにチンポをおったてちゃって若いわね。クククッ、おかしい……」
健志の股間に目をやり、手を伸ばして膨らみを確認した彩は満面の笑みで楽しそうに笑う。
ブラウスの胸元とスカートの裾を直し終えたタイミングでエレベーターは目的のフロアーに着く。
チンッ……シャッ~……ドアが開くと食事を終えたらしいカップルがエレベーターを待っていて軽く会釈して降りる彩の顔は上気している。
「フゥッ~、久しぶりだから昂奮する。まだドキドキしてる、確かめてみて」
健志の手を取って胸に押し付け、
「ねっ、ドキドキしているでしょう??」
「ごちそうさま……」
声と共に、店を出てきた客と目が合い羞恥で健志の胸に顔を埋めると抱え込まれ、足音が遠ざかると顎に指をかけて小柄な彩は上向きにされて唇を合わされる。
「ハァハァッ……イヤンッ、アソコが濡れちゃったみたい」
優子から変身した彩は、最近疎遠になったとはいえ夫や学生時代から互いに親友と呼ぶ栞でさえ想像する事もできないほど妖艶で奔放な女性になっている…
「食事する時間しかないのが残念だなぁ。こんなにエッチで可愛い彩が目の前にいるのに」
「少しくらいなら遅くなっても好いよ。今晩、健志が眠れる程度には興奮を冷ましてあげようか、クククッ」
よく分からないけどスイス料理ならこれだろうとチーズフォンデュとオイルフォンデュ、飲み物はどんな料理でも辛口の白ワインと言う健志に合わせてオーダーする。
スイスワインと共に食べるチーズフォンデュのパン、オイルフォンデュの肉で十分に満足した二人は何種類かのチーズでワインのボトルを空けて満足する。
「この後、そうね二時間までならいいよ」
「えっ、ほんとう??もし、彩に予定がなければ、この店を出てエレベーターが一階についてドアが開くまでに考えさせてくれよ」
「健志がどんなことを考えるか楽しみ。期待を裏切らないでね……ウフフッ」
「いらっしゃいませ。雨は降ってる??」
「冷たい雨が降り始めたよ」
「天気予報が当たったんだ……今日は居る??」
「居るよ。来るか??」
「うん、冷たい雨の夜は温もりが欲しい」
「待っているよ。眠っていたら起こしてくれよ」
「そうする。他のお客さまに見えないようにマッサージして欲しい」
水割りを作り終えた女は自然な振る舞いで男の腿に右手を置き、男はその手を優しく包み込む。
手の平に親指を押し当てて残る四本の指で甲を擦り始める。
「気持ちいい。専任のマッサージ師として雇いたいくらい」
「クククッ、それは光栄だね」
「ウソ、あなたのテリトリーには入れないし入れてくれない。共通のパーソナルスペースが欲しい……二人だけのスペースが欲しいのに……」
「いつでも俺の部屋に入れるし、俺も亜紀の部屋で眠り込んでいるベッドに黙って入ったこともある」
「そうね……」
手のマッサージを終えた男は指を一本ずつ包み込んで優しく揉み解し、指先から疲れを抜き取っていく。
「手や指だけじゃなく身体中が温かくなってくる、気持ちいい」
「失礼します。亜紀さんお願いします」
「ごめんね、指名が入ったみたい。待っていてくれる??」
「いや、適当に帰るよ」
「うん、それじゃ後でね」
亜紀が席を立った後、30分ほど絵里奈と会話を楽しんだ男は席を立つ。
背中に亜紀の視線を感じたが振り返る事もなく店を出た男は、暗い空から降ってくる雨を気にする様子もなく歩き始める。
シャワーを浴びて素肌にパジャマを着け、ベッドに入り込むとすぐに睡魔に襲われて亜紀が来るのを気に掛けながらも夢の中の住人になる。
男と同じマンションに住む亜紀は自分のフロアではなく男の部屋があるフロアボタンを押す。
カチャッ……バタンッ……静かにした積りでも深夜のドアの開閉は驚くほどの音を立てる。
ベッドに近付き目を閉じたままの男の額に唇を合わせても目を覚ますことはなく、優しさの中に寂しさを交えた笑みを浮かべてバスルームに向かう。
シャンプーの泡と共に疲れを流し去り、入念に歯磨きをした亜紀はバスローブをまとい、髪にブラシを入れながらベッドに近付き、ナイトテーブルを見て顔を綻ばせる。
「クククッ、気付いてくれないのかと思ってガッカリしたんだよ」
「亜紀の部屋に帰っちゃおうと思ったか??」
「思った、二度とここには来ないようにしようと思ったよ……クククッ、飲ませて、喉が渇いちゃった」
バスローブを剥ぎ取って素っ裸にした亜紀を抱きかかえ、シャワーを浴びている最中に用意したミネラルウォーターを開栓して口移しで流し込む。
ゴクッ、喉を鳴らして飲み込む亜紀を見つめる男の動悸が激しくなり、そのまま侵入させた舌を絡ませて濃厚なキスをする。
亜紀は両手を首と背中に回してきつく抱きしめ、貪るように男の唾液を啜る。
ハァハァッ……いったん離れて見つめ合い、相手の瞳に恋慕の想いを感じ取った二人は突き出した舌をつついたり絡ませたりしながら宙で踊らせ、上下の唇を甘噛みしながら背中を擦り身体を擦りつける。
亜紀の背中を支えて寝かせた男はミネラルウォーターを胸の谷間に垂らして肌に広がる水を吸い取っていく。
「クククッ、くすぐったい」
「動いちゃダメだよ」
膨らみの先端に垂らして直ぐに舐めとり、それを二度三度と繰り返すうちにピンクの乳首は勃起して上気した亜紀は息を荒げる。
「ダメ、舐めさせて、いつもより昂奮しているの、我慢できない」
身体を入れ替えた亜紀は男の両足の間に潜り込んで股間に顔を埋め、ジュルジュル音を立ててフェラチオに耽る。
満足の笑みを浮かべた男は身体の向きを変えるように促して亜紀が上になったシックスナインの恰好になる。
目の前で綻びを見せる割れ目をゾロッと舐めると、男を跨ぐ太腿がフルッと震えて悩ましいことこの上ない。
「イヤンッ、いつものようにビラビラを吸ったり噛んだりしてほしい」
亜紀の声を無視して会陰部にベロリと舌を這わせ、裏門の窄まりを舌先でツンツンとつつく。
「ダメッ、今日は洗っただけで中をきれいにしてないから恥ずかしい」
「好きな女の身体だよ、何もかも俺のモノだろ。亜紀のすべてを欲しい」
「クククッ、好きな女なの??嬉しい、私はあなたのモノが欲しい……入れて、あなたのモノで私を啼かせて」
「ウググッ、クゥ~、くる、くる、あなたのモノがアソコに入ってくる」
互いの身体に馴染んだ二人は激しい刺激がなくとも快感を高めていく。
「ウネウネと俺のモノを奥に吸い込もうとする。気持ちいい」
「あなたのモノが入ってくるとアソコが勝手に蠢いちゃうみたい。動きを止めて……アァッ~、分かる??分かるでしょう??何もしなくてもアソコが勝手にウネウネするの……こんな事って、クゥッ~、あなたが好き」
満足した二人はシャワーを浴びてベッドに入り、腕枕された亜紀は心地好い疲れを感じながら目を閉じる。
「おやすみ……あれっ、亜紀、亜紀……寝ちゃったか……店で二人に共通するパーソナルスペースが欲しいって言っただろ。今はこのマンションが秘密を共有するスペースだけど、もう少し狭くして、どちらかの部屋で一緒に住もうか、どう思う??」
「私が眠ってないって知ってる??」
「分かっているよ、亜紀の事は亜紀本人よりも知っている積りだよ」
「そんな事を言うと泣いちゃうよ……絵里奈ちゃんにね、あなたと付き合っているだろうって言われたの」
「そうか、今度、絵里奈ちゃんを呼んで三人で食事しようか。どう思う??」
「絵里奈ちゃんに、この部屋が私たち二人のパーソナルスペースで秘密の場所、誰にも邪魔されない場所だよって宣言するの??」
「そうだよ。俺のパーソナルスペースには亜紀も入れないって言っただろ??」
「うん、言ったよ。一緒に住んでくれるなら、そんな事は気にならないから忘れてもいいよ」
「俺が亜紀の事を大切な人だと思っていることは知っているだろう??」
「うん、大切にされているし愛されていると思っているよ」
「亜紀もそうだろうけど、大切な人だからこそ言いにくい事もあるだろう??心配させちゃいけないとか、色んなことを考えてさ……出来るだけ、可能な限り話すようにするけど、そんな気持ちが入り込めない秘密の場所って思わせていることも理解して欲しい。亜紀が一番大切な人って事に嘘はないから」
「うん、信じる。ありがとう……必要な荷物を少しずつ運んできてもいい??」
「嬉しいよ……可愛いよ、亜紀。おやすみ」
「おやすみのキスが欲しい」
<< おわり >>
佐緒里と内藤 -39
シャワーで汗と共にセックスの痕跡も洗い流した佐緒里は黒いハーフバックショーツを着けて内藤の白いシャツを取り出す。
「これにする。白は似合うかなぁ……あなたと二人きりの時は好い女でいたいから」
「白いシャツの下で見え隠れする黒い下着、エロいって言うより、かっこいいよ。クールだ」
「クール、そんな言葉を使うって意外……それより、お腹が空いた。待っていて、何か用意してくるね」
背筋が伸びて膝下を伸ばして歩く後ろ姿は颯爽として好ましく、白いシャツを捲り上げて剥き出しになった白い腕が色っぽい。
「後ろ姿を見ているでしょう??刺すような視線を感じる……サービスしてあげようか、昂奮して鼻血を流さないでね」
振り向くことなく内藤が見つめていることを指摘した佐緒里は、艶めかしく腰を振る。
「やっぱり好い女だよ。男を挑発することに長けているし、いざセックスとなれば仁王立ちの前で跪いて吐き出したモノを飲んでくれるし、SM遊びも厭わない。一度でも夜を過ごすと虜になっちゃうだろうな。昼は淑女で夜は娼婦、この言葉は佐緒里を指しての言葉かと思うよ」
「私の事をそんな風に思っているの??冗談だよね……あなたが相手だからフェラチオもしたいし、苛められたいの。誰が相手でもって事じゃないよ、独りエッチで満足していたって言ったでしょう。忘れたの??」
「ごめん、フフフッ……」
音もなく近寄った内藤は背後から抱きしめて髪に顔を埋め、息を吸い込んで佐緒里の匂いで胸を満たす。
「どう??私の匂いがする??」
「佐緒里の好い匂いがするよ……フゥッ~」
「イヤンッ、息を吹き付けられると変に温かくて気持ちワル~イ……あなたが吸い込んだ匂いはシャンプーの香り。私の匂いじゃないよ、気付いてくれなくて残念」
「クククッ、分かっているさ。毎日使っているシャンプーだよ、それにオレはアロマポット、アロマキャンドル、お香などにも興味がある。間違えるわけがないだろ」
「そうね、そうだった……それより私は包丁を持っているの。危ないから離れてくれる??」
「いやだっ、佐緒里から離れたくない」
内藤は抱きしめるだけではなくシャツのボタンを外そうとし、クククッと笑った佐緒里は包丁の峰を手の甲に押し付ける。
「あなたと一緒に暮らせば毎日、こんな風にしていられるんだよね……結論を早まっちゃったかな」
シリアル、焼きバナナ、サーモンとアボカドのサラダを手際よく準備しながら、
「卵は任せてもいいかな??」
「いいよ、チーズオムレツで好いね??」
フワフワのチーズオムレツとリンゴジュースをテーブルに運び、外の景色を見ながら美味そうに頬張る。
後片付けを終えた二人はミルクティを淹れて元の場所に戻り、ソファに寄りかかって床に座る内藤の足の間に入り込んだ佐緒里はティーカップを両手で持って満足そうに眼を閉じる。
「私の両親や美香ちゃんに対して知られちゃいけない秘密を持った二人でしょう??私のせいだと分かっているけどね……美香ちゃんや両親の前ではいつまでも偽者でいなきゃね。本当の姿を晒すのは、あなたと私、二人きりの時」
「クククッ、困った人だなぁ、佐緒里は」
「そう、悪い女なの私は……何度も言うけど、美香ちゃんに優しくしてあげてね、本当に好い子だよ」
内藤の左手は身体を預ける佐緒里を抱きかかえて胸に伸び、その手に重ねた左手は逞しい腕を擦る。
「好い事を思いついた。私の下着を置いて行ってもいいでしょう??美香ちゃんを大切にしてもらいたいけど、この部屋は秘密の場所にしたい。ねぇ、いいでしょう??」
「構わないけど、昨日のレンタルルームを秘密の部屋にした方が良かないか??」
「いじわる、アソコは二人だけの秘密の場所じゃないもん。私の知らない女の人も縛られたり鞭で打たれたりして啼くんだよ……決めた、この部屋は美香ちゃんにも譲らない」
振り向いた佐緒里は笑みを浮かべ、
「この部屋に入る女は私だけ、約束の印を頂戴」と囁いて目を閉じ、顎を突き出す。
内藤は佐緒里の魅力に吸い寄せられるように唇を重ねる。
<< 一旦、終わり >>
佐緒里と内藤 -38
キスを催促する佐緒里の瞳は内藤から逸れることなく黒目を開いて真っすぐに見つめる。
目は口ほどにものを言う、あるいは目は心の窓と言われるが、その言葉通りに内藤の心の内を読み取ろうとし、内藤もまた見つめる瞳から視線を逸らすことなく見つめ返す。
「フフフッ、私の直感があなたは信じても好い男性だと言っている」
「ありがとう、佐緒里の記憶の隅に残る元ご主人の想い出に重ね塗りをしちゃおう」
「うん、記憶はかなり薄くなっているから消すのは簡単だと思う。あなたとの想い出に塗り替えたい」
「楽しかったことも嫌なこともひっくるめて、すべてが佐緒里だよ。何かの記憶を無理やり消し去るのは好きじゃないな……油絵を描くときに下塗りをするらしいけど、色を重ねるから深みが出るらしいよ。それに重ねるから少々、間違えても修正が効く。人生と似ていると思わないか??」
「一度や二度間違えても、やり直しがきくし、それが人間の深みになるって事??」
「うん、オレはそう思うよ。勿論、押し付けるわけじゃないけどね」
「分かった、無理やり嫌な男の記憶を忘れようとするのは止める。楽しい想い出を積み重ねて自然と、そんな事もあったなぁって思えるようになればいいな……それより、油絵を描くの??」
「いいや、字も絵もヘタッピだから書かない。恥はよく掻くけどね」
「ふ~ん……油絵を描く人はきれいだった??……イヤンッ、大切な事を聞いている最中なのにそんな事をされたら気持ち善くなっちゃう」
顔を寄せて耳に息を吹きかけると佐緒里はくすぐったい様な気持ちいいような刺激を受けて身体をくねらせる。
「えっ、どうだったかな??憶えてないよ」
「そうなんだ、油絵を描くのは、きれいな女性なんだ。今も付き合っているの??……付き合っていたら、クククッ、邪魔しちゃう」
肩に顎を載せるような振りをして首に吸い付き、キスマークをつける。
「オッ、痕が付いたか??美香ちゃんに見せようか……想い出の世界に住んでいる人だよ。付き合っている人の事を寝物語するほど嫌な男じゃないよ」
「クククッ、美香ちゃんに見せちゃダメ……付き合ってないって信じる。今、付き合っているのは美香ちゃんだけでしょう??私は妹分だと思っている美香ちゃんに隠れてあなたに抱いてもらう。スリルや背徳感で燃え上がる事もあるけど、美香ちゃんに申し訳ないと思う気持ちが、私の経験を伝えて一人前になる近道になればいいなと思っているの、フフフッ、本当だよ」
美香に対する申し訳ないと思う気持ちを言い訳する佐緒里は能弁にする。
「悪い女だな。美香ちゃんに代わってお仕置きをしなきゃいけないな」
「イヤンッ、怖い。許して……クククッ、シャワーを浴びている隙にシャッターを下ろしてキャンドルの灯り、部屋は艶めかしいお香の匂いに満たされていた。昨日はSMルームのあるレンタルルーム。意外なことが続いたから怖い」
「それが好いんだろ。でも、今はヒィヒィ身悶えるほど突きまくるだけだよ……そういや、キスを催促されたんだっけ」
「そんな言い方をされたら冷めちゃうよ」
腰に添えていた内藤の右手が頬を擦ると全身の力が抜けてトロンとなり、静かに目を閉じて内藤が唇を合わせても動くことなく沈黙を続ける。
舌先が上下の唇を刷いたり突いたりして動きを誘っても佐緒里の両手は背中を擦るばかりで、上唇を甘噛みして震わせ下唇を甘噛みすると、フフンッと艶めかしい声が漏れる。
舌先を強引に口腔に捻じ込もうとすると固く唇を合わせて舌の侵入を拒もうとする。
閉じたままの佐緒里の目を見つめる内藤は目元を緩め、右手で胸の膨らみを掬い上げてヤワヤワと揉みしだく。
「イヤンッ、そんな事をされたら気持ち善くなっちゃう。ダメッ……ウグッ、クゥッ~、ウッウゥッ~、そんなこと」
乳房を揉まれ先端を摘ままれては可愛くキスを拒否する抵抗も儚く、内藤の舌の侵入を受け入れる。
ウグッ、フグッフグッ……佐緒里の手が内藤の背中に回り、固く抱き寄せて自らの舌を侵入させて絡ませる。
濃厚なキスを終えた佐緒里の表情に羞恥が宿り愛おしさが募る。
憎からず思い、慕ってくれる美香の顔が浮かぶものの性感の高まった内藤には今更止める術もない。
佐緒里の腰と背中に手を添えて身体を支え、ベッドのクッションを利用して突き上げる。
「佐緒里のマンコがクイクイ締まるし奥がコリコリして気持ちいいよ」
「アンッ、腿を大きく開かれて突き上げられるとチンチンが一番奥、子宮口をつつくんだもん。痛痒くて苛められている感じがする……そう、奥でチンチンを感じる」
乱れ髪に手櫛を入れた内藤は、
「可愛いよ、こんな表情をオレ以外の男に見せるんじゃないぞ」
「嬉しい、もっと言って。お前はオレの女だと言って」
「佐緒里はオレの女だ。オレの腕の中にいる時だけ女になればいい」
「うん、あなた以外の男に抱かれたりしない。気持ちいいの、逝っちゃいそう」
首に両手を回して足を踏ん張り、腰を妖しく蠢かしながら身体を上下する佐緒里は自ら呼び込んだ快感を堪えるために下唇を噛んで目を閉じる。
「クゥッ~~、ダメ、気持ちいいの、我慢できない。逝っちゃう、逝っちゃうよ」
「オレもだ、逝くよ。出しちゃうよ」
「ちょうだい、あなたの濃いのをいっぱい頂戴」
「ウッウッ、クゥッ~、出ちゃうよ、クゥッ~」
「ヒィッ~、すごい、すごい、奥に、あなたの熱いモノがビュッと感じた……最後まで搾り取っちゃう」
吐き出したモノにとどまらず、すべての精液を搾り取ろうとして佐緒里は下半身を蠢かす。
「勘弁してくれよ、くすぐったい」
「クククッ、男ってだらしない。女はほんの少し休憩すればすぐにできるよ」
「悪いな、横にならせてもらうよ」
佐緒里を抱きかかえて抜け落ちないように気遣いながら対面座位から対面側位の恰好に変化する。
「知ってる??ここにキスマークが付いているんだよ」
佐緒里の指が首を擦り、自分にも付けて欲しいと言う。
店での衣装から完全に隠れる場所に唇を近付けると、
「そんなところじゃ嫌、首は困るけどオッパイが好い。胸元が隠れるドレスを着てあなたと私、二人だけの秘密に胸を焦がすの……早くっ」
乳房にくっきりと残る痕をつけると満足そうに笑みを浮かべる。
「アンッ、ダメ、抜けちゃう、抜けちゃうよ」
内藤は手を伸ばしてティッシュを取り、二人のつなぎ目に添えてゆっくりと身体を離し、上半身を持ち上げる。