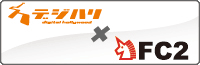桜子 -2
ホテル
「着いたよ」
「鴨川シーワールドか、意外です……シャチのショーをやっているんだよね??」
平日なのでシャチのショーを見るのに並ぶことなく、席も自由に選ぶことが出来た。
水しぶき除けのポンチョを買って前の方に座ると、
「ポンチョはシャチがジャンプした時の水しぶき除けなの??そんなにスゴイの??」
「すごいよ、イルカとはサイズが違うからね。夏ならずぶ濡れになって、そのまま海に行くのもいいけど今はそんな季節じゃないだろう」
「キャッ~……すごい。想像以上の水しぶき。ポンチョがなければずぶ濡れになるところだった」
顔や髪に掛かった水を気にすることもなく笑顔ではしゃぐ桜子は、優雅でエレガントな女性という印象をかなぐり捨てて楽しみ、見つめる柏木の表情には自然と笑みが浮かぶ。
イルカやアシカのショーも童心に帰ったように楽しみ、クマノミやクラゲの水槽の前では自然と腕を組み初めてのデートとは思えないほど二人の距離が縮まっていた。
「もっと見ていたいけど帰ろうか。もう一つ見せたいものがあるんだ」
「うん、分かった」
往路を逆に走り、アクアラインを目指す。
「正直に言うと、お客様に誘われて同伴することもあるけど、今日のように楽しかったのは初めて。はしたなかったけどお誘いしてよかった」
「同伴でシーワールドは無理だろうし、クジラや地魚も地元で食べると雰囲気や空気が調味料になるだろうし……但し、夕食は同伴の食事と比べないでくれよ。先に言っとくけど、しゃれた店を知らないからね」
「謙遜だろうけど、どこで食べても柏木さんとなら幸せな気持ちになれる。今度は誘って欲しいな、次も私が誘うとはしたない女だって思われるだろうから、覚えておいてね」
「あぁ、憶えとくよ」
アクアラインを走り始めると楽しかった今日に別れを告げ、何かを期待させる夜を迎えるために太陽が西の空をオレンジ色に染めて沈み始める。
「きれい……もう一つ、見せたいモノって夕陽??私が夕陽を見たいって言ったから??」
「そうだよ。海ほたるの展望デッキから夕陽を見よう。海に沈むって訳にはいかないけど、心が洗われるほどきれいだよ」
海ほたるの展望台に上ると周囲を海に囲まれているために潮の香が漂い、潮風が桜子の髪と戯れる。
乱れ髪を整えようとして手櫛を入れるのさえ好ましく、展望デッキから見る景色は素晴らしいよと言った事も忘れて桜子に見入る。
「気持ちいい。いつもは店に向かう時刻なのに羽田空港発着の飛行機や東京湾を行きかう船、360度の眺望の海を眺めているなんて信じられない」
「天気のいい昼間は富士山やスカイツリーも見えるけど、今は夕陽の美しさを堪能しよう」
日没を迎える寸前の太陽が別れを惜しむかのように海に一筋、オレンジ色に輝く道を作り周囲の空を朱く染める。
オレンジ色に輝いていた太陽が三浦半島の山陰に掛かると朱く色を変えてゆっくりと姿を隠していく。
デッキは灯りに照らされているものの対岸は暗くなり、太陽に隠れていた富士山が墨絵のような姿を現す、
幻想的な景色を見ながら二人でいることの幸せを感じ、腰に添えた柏木の手が桜子を抱き寄せ、桜子は肩を寄せて柏木の横顔を見つめる。
言葉がなくとも二人の心が会話を始め、今見た景色に感動する周囲を気にすることなく身体を寄せ合って車に戻る。
海ほたるを出発して今日という日を笑顔で語り合っていた二人は、湾岸線を走る頃には互いの横顔を盗み見るようして次第に無口になっていく。
柏木はベッドを共にするための言葉を探しあぐね、桜子は夕食が終われば家に送ると言われるのではないかと不安になる。
首都高を臨海副都心で下りて目的のホテルに着くと二人の緊張は頂点に達する。
「フゥッ~、着いたよ。しゃれた店は知らないから無難にこのホテルのレストランでディナーにしよう」
「えっ、はい」
車を降りてドアを開け、桜子に手を伸ばすと揃えた両足を地面について柏木の手を支えにして優雅に降り立ち周囲を見回す。
柏木が小さなバッグを持っているのを見て桜子の表情が緩み、柏木は桜子の視線がバッグに向くのを見て苦笑いを浮かべる。
「良かった、食後直ぐに家に送ろうと言われることはなさそう……そうでしょう??」
「直ぐに送るとなると、ワインも飲めない味気ないディナーになっちゃうからね。桜子さんを送るのは明日になっちゃうかもしれないな」
「そうなの……ウフフッ、今日は休みをもらっているから平気だよ」
帰りたくないと口にせずとも思いは通じ、一層親しげにフロントに向かう。
フロントカウンターでチェックインを済ませてベルガールの案内に従う二人の手はしっかりとつながり、二人だけの秘密を作る予感で口元が綻び、つなぐ手に力を込める。
ベルガールが立ち去り二人だけになると柏木は豹変し、桜子を壁に押し付けて瞳の奥を覗き込む。
「いやっ、恥ずかしい。私の真意を探ろうとするように見つめられるとドキドキする……何も嘘を吐いてないし、こんな風に二人きりになりたかっただけ」
「オレもドキドキして吐きそうなくらいだよ」
「クククッ、私の顔に向かって吐いちゃイヤッ……お口なら飲み込んでもいいよ」
そうと聞いては尻込みするわけにもいかず、鳥が餌を啄むように唇をチュッチュと合わせ、桜子の両手が背中に回って力がこもると柏木の右手が頬を擦り、上唇、下唇と甘噛みして舌を侵入させる。
「アンッ、ハァッ~……こんな風にしてほしかったの、気持ちいい」
ハァハァッ……唇を重ねて舌を絡ませ、両手で背中や腰を撫で擦って思いの丈を伝えあった二人は瞳をメラメラと燃え上がらせる。
「長い夜になりそうだけど、まだまだ早い。食事にしようか??」
「少し時間をください」化粧ポーチを持ってバスルームに向かった桜子は戻ってくると、
「化粧スペースが独立しているのを知っていたの??……ふ~ん、知っていたんだ。行き届いた思いやりは嫉妬の対象になるわよ」
「憶えとくよ、行こうか」
「着いたよ」
「鴨川シーワールドか、意外です……シャチのショーをやっているんだよね??」
平日なのでシャチのショーを見るのに並ぶことなく、席も自由に選ぶことが出来た。
水しぶき除けのポンチョを買って前の方に座ると、
「ポンチョはシャチがジャンプした時の水しぶき除けなの??そんなにスゴイの??」
「すごいよ、イルカとはサイズが違うからね。夏ならずぶ濡れになって、そのまま海に行くのもいいけど今はそんな季節じゃないだろう」
「キャッ~……すごい。想像以上の水しぶき。ポンチョがなければずぶ濡れになるところだった」
顔や髪に掛かった水を気にすることもなく笑顔ではしゃぐ桜子は、優雅でエレガントな女性という印象をかなぐり捨てて楽しみ、見つめる柏木の表情には自然と笑みが浮かぶ。
イルカやアシカのショーも童心に帰ったように楽しみ、クマノミやクラゲの水槽の前では自然と腕を組み初めてのデートとは思えないほど二人の距離が縮まっていた。
「もっと見ていたいけど帰ろうか。もう一つ見せたいものがあるんだ」
「うん、分かった」
往路を逆に走り、アクアラインを目指す。
「正直に言うと、お客様に誘われて同伴することもあるけど、今日のように楽しかったのは初めて。はしたなかったけどお誘いしてよかった」
「同伴でシーワールドは無理だろうし、クジラや地魚も地元で食べると雰囲気や空気が調味料になるだろうし……但し、夕食は同伴の食事と比べないでくれよ。先に言っとくけど、しゃれた店を知らないからね」
「謙遜だろうけど、どこで食べても柏木さんとなら幸せな気持ちになれる。今度は誘って欲しいな、次も私が誘うとはしたない女だって思われるだろうから、覚えておいてね」
「あぁ、憶えとくよ」
アクアラインを走り始めると楽しかった今日に別れを告げ、何かを期待させる夜を迎えるために太陽が西の空をオレンジ色に染めて沈み始める。
「きれい……もう一つ、見せたいモノって夕陽??私が夕陽を見たいって言ったから??」
「そうだよ。海ほたるの展望デッキから夕陽を見よう。海に沈むって訳にはいかないけど、心が洗われるほどきれいだよ」
海ほたるの展望台に上ると周囲を海に囲まれているために潮の香が漂い、潮風が桜子の髪と戯れる。
乱れ髪を整えようとして手櫛を入れるのさえ好ましく、展望デッキから見る景色は素晴らしいよと言った事も忘れて桜子に見入る。
「気持ちいい。いつもは店に向かう時刻なのに羽田空港発着の飛行機や東京湾を行きかう船、360度の眺望の海を眺めているなんて信じられない」
「天気のいい昼間は富士山やスカイツリーも見えるけど、今は夕陽の美しさを堪能しよう」
日没を迎える寸前の太陽が別れを惜しむかのように海に一筋、オレンジ色に輝く道を作り周囲の空を朱く染める。
オレンジ色に輝いていた太陽が三浦半島の山陰に掛かると朱く色を変えてゆっくりと姿を隠していく。
デッキは灯りに照らされているものの対岸は暗くなり、太陽に隠れていた富士山が墨絵のような姿を現す、
幻想的な景色を見ながら二人でいることの幸せを感じ、腰に添えた柏木の手が桜子を抱き寄せ、桜子は肩を寄せて柏木の横顔を見つめる。
言葉がなくとも二人の心が会話を始め、今見た景色に感動する周囲を気にすることなく身体を寄せ合って車に戻る。
海ほたるを出発して今日という日を笑顔で語り合っていた二人は、湾岸線を走る頃には互いの横顔を盗み見るようして次第に無口になっていく。
柏木はベッドを共にするための言葉を探しあぐね、桜子は夕食が終われば家に送ると言われるのではないかと不安になる。
首都高を臨海副都心で下りて目的のホテルに着くと二人の緊張は頂点に達する。
「フゥッ~、着いたよ。しゃれた店は知らないから無難にこのホテルのレストランでディナーにしよう」
「えっ、はい」
車を降りてドアを開け、桜子に手を伸ばすと揃えた両足を地面について柏木の手を支えにして優雅に降り立ち周囲を見回す。
柏木が小さなバッグを持っているのを見て桜子の表情が緩み、柏木は桜子の視線がバッグに向くのを見て苦笑いを浮かべる。
「良かった、食後直ぐに家に送ろうと言われることはなさそう……そうでしょう??」
「直ぐに送るとなると、ワインも飲めない味気ないディナーになっちゃうからね。桜子さんを送るのは明日になっちゃうかもしれないな」
「そうなの……ウフフッ、今日は休みをもらっているから平気だよ」
帰りたくないと口にせずとも思いは通じ、一層親しげにフロントに向かう。
フロントカウンターでチェックインを済ませてベルガールの案内に従う二人の手はしっかりとつながり、二人だけの秘密を作る予感で口元が綻び、つなぐ手に力を込める。
ベルガールが立ち去り二人だけになると柏木は豹変し、桜子を壁に押し付けて瞳の奥を覗き込む。
「いやっ、恥ずかしい。私の真意を探ろうとするように見つめられるとドキドキする……何も嘘を吐いてないし、こんな風に二人きりになりたかっただけ」
「オレもドキドキして吐きそうなくらいだよ」
「クククッ、私の顔に向かって吐いちゃイヤッ……お口なら飲み込んでもいいよ」
そうと聞いては尻込みするわけにもいかず、鳥が餌を啄むように唇をチュッチュと合わせ、桜子の両手が背中に回って力がこもると柏木の右手が頬を擦り、上唇、下唇と甘噛みして舌を侵入させる。
「アンッ、ハァッ~……こんな風にしてほしかったの、気持ちいい」
ハァハァッ……唇を重ねて舌を絡ませ、両手で背中や腰を撫で擦って思いの丈を伝えあった二人は瞳をメラメラと燃え上がらせる。
「長い夜になりそうだけど、まだまだ早い。食事にしようか??」
「少し時間をください」化粧ポーチを持ってバスルームに向かった桜子は戻ってくると、
「化粧スペースが独立しているのを知っていたの??……ふ~ん、知っていたんだ。行き届いた思いやりは嫉妬の対象になるわよ」
「憶えとくよ、行こうか」