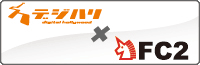彩―隠し事 79
日曜日 貞淑な妻に戻る
健志の胸に顔を埋めて抱きかかえられるようにして眠っていた彩は食欲を刺激する匂いで目を覚ます。
そばにいたはずの健志は手に触れることがなく、視線を巡らしても姿はない。勝手知ったる部屋とばかりに健志の白いシャツを取り出して下着を着けずに素肌に羽織って、匂いの元を探してベッドルームを出る。
前夜、彩と健志の卑猥な遊びの舞台となったソファは何事もなかったかのようにいつもの場所にある。
陽光が差し込む部屋の眩しさを避けて手をかざし、ベランダを見ると昨日とは別のチノパンにシャツを着た健志が朝食を用意したテーブルを前にして椅子に座り、
「おはよう。今日の彩は昨夜とは別人のようだよ、清楚で上品。パイパンマンコの持ち主でセックスに貪欲なスケベ、そんな雰囲気は微塵も感じさせない……オレが知っている彩が本物なのか、今、目の前にいる名前も知らない清楚な女性が本物なのか、知れば知るほど魅力的な女性だよ」
「クククッ……褒め言葉として受け取っとくね。でも、今の言葉は正確じゃない、昼間の清楚で上品な時は健志には会わないの……だから、ほら……」
白いシャツの裾を引き上げると、守るモノが何もなく、くすみの少ない股間が姿を表す。
「ねっ、健志の知っている彩のママでしょう……おはようのキスをしてくれないの??」
彩を見つめる健志の眩しそうな顔に自然と笑みが浮かび、そんな健志を見つめる彩の表情も屈託なく緩む。
「白いシャツがお日さまを反射して眩しいの??」
「嫌な女だな。キラキラした彩が眩しいんだよ。夜の灯りに慣れ過ぎたようだよ」
大きく開いた両手を彩に向けて伸ばすと、その間に入り込んで腿を跨いで首に両手を回し、
「昨日は気持ち良かったよ。知らない人に見られるかもしれないというドキドキ感も味わえたし、健志の吐き出した火傷するほど熱い満足の証も受けたし……今日は、お日さまが眩しい」
空を見上げる彩は目を眇め、いかにも眩しそうな表情になる。
「可愛いな。昼間の彩も魅力的な女性だろうと思うと残念だよ」
「うちの旦那をぶっちめて昼も夜も健志のモノにしたい??」
「そうだな、できる事ならそうしたいと思うよ」
「嬉しい、そう言ってくれるだけで彩は幸せ。本当にそんな事をするには全てを捨てる覚悟をしなきゃいけないけど……彩には無理」
「仕事??それとも、ご主人??」
「両方。今はピンチだけど好きで一緒になった人だし、健志も言ったでしょう。彩も主人以外の人とエッチすれば気持ちが分かるだろうし優しくなれるって。あれは彩を抱くための方便だったの??」
「そんな積りはなかったけど……改めて考えると何とも言えないな」
「そうなんだ……お腹が空いた。食べてもいい??」
牛乳だけのシンプルなオートミール、ベーコンと玉ねぎとキャベツのスープ、プレーンオムレツとソーセージ、ブロッコリーなどの温野菜がテーブルいっぱいに並んでいる。
どれもこれも湯気と匂いが食欲をそそり、たっぷりの牛乳を入れたミルクティが身体を芯から温めてくれる。
駅周辺の煌びやかな灯りは消えたものの健康的な賑わいは日曜の朝も絶えることがない。
「ねぇ、聞いてもいい??……夜の繁華街に人が集まれば集まるほど明るさが増し、それに伴って陰も濃くなるって言ったよね。影は悪なの??」
「どうしてそんな事を聞くのか分からないけどオレが思うのは、人間の欲望を満足させるのは困難だと思う。意識しないけど、何か満たされない思いが影となるんだと思うよ」
「うん、大体わかった。実はね明日、担当役員に新規プロジェクトの説明をしなければいけないんだけど、なんかヒントをもらったような気がする。それと、風俗って新しい業態って言うか次から次に法の網をくぐるような店が出来るでしょう、それはどう思うの??」
「欲望に限りがないってのが一番の理由で需要と供給って事だと思うけど、新規業態の店が出来て、その店が人気になれば、どうするか??」
「競合店や新規加入業者はどうするの??」
「これまで通りの店も当然あるだろうね。真似をする、その店を上回るサービスを考える……一番新しいって言うのは常に目標になるから、近い将来、一番じゃなくなる可能性が大きいだろうね。常に先を見て歩き続けることが必要だと思うよ」
食べる手を止めて健志の話を聞く彩は、何かが閃き頭の中が自分の意思を超えて駆け回るのを意識する。
「何か考えているようだけど、夜の街の妖しい蠢きが昼間の彩の仕事のヒントになるの??」
「まだ、はっきりと、まとまらないけど、イメージが掴めそうな気がする。昼も夜も対象は人間、ヒントはあると思うの」
すべての皿を空にしてミルクティを飲み干した二人は後片付けを終えて再びベランダに戻る。
椅子に座る健志の腿に座った彩はシャツのボタンを外して乳房に残る縄模様を愛おし気になぞる。
「誰かに見せてあげたい……夜の私は彩という女に変身して、こんな事をして楽しんいるんだよって」
「この白いムチムチとした身体はオレの許可なしで他人に見せちゃだめだよ。分かった??」
「彩は健志のモノなの??健志の女なの??……そんな事を言われて悦ぶ女だったんだ、彩は……ウフフッ、キスして」
唇を合わせて互いの身体を擦りながらも、彩が清楚な人妻に戻る時間が近付いているという現実がそれ以上の事を躊躇わせる。
「どうする、途中まで送ろうか??」
「駅まで歩いて電車に乗るから健志はここから見ていて……それより、縄やオモチャを他の人に使っちゃ嫌だよ」
「そんな事をするわけないよ。大きい紙袋に入れて彩が封印のサインをしとけばいいよ。オレが信用できないならね」
「クククッ、信用するけど、秘密めいていて楽しそう。それを採用」
坂道を駅に向かう彩を見送る健志は、
「あや~、浮気しちゃだめだぞ」と、他人を気にする様子もなく大声で叫んで手を振る。
彩は、笑みを浮かべる人や驚いた表情で彩と健志を見比べる人たちに軽く会釈し健志に手を振り足早に歩き始める。
駅に向かう時間と電車の時間、最寄り駅から自宅までの時間に彩から普段の自分に戻り、健志との記憶を封印して貞淑な妻に変身し、出張だと言って浮気する亭主を笑顔で迎えることが出来そうだと思う自分に恐れを抱く。
健志の胸に顔を埋めて抱きかかえられるようにして眠っていた彩は食欲を刺激する匂いで目を覚ます。
そばにいたはずの健志は手に触れることがなく、視線を巡らしても姿はない。勝手知ったる部屋とばかりに健志の白いシャツを取り出して下着を着けずに素肌に羽織って、匂いの元を探してベッドルームを出る。
前夜、彩と健志の卑猥な遊びの舞台となったソファは何事もなかったかのようにいつもの場所にある。
陽光が差し込む部屋の眩しさを避けて手をかざし、ベランダを見ると昨日とは別のチノパンにシャツを着た健志が朝食を用意したテーブルを前にして椅子に座り、
「おはよう。今日の彩は昨夜とは別人のようだよ、清楚で上品。パイパンマンコの持ち主でセックスに貪欲なスケベ、そんな雰囲気は微塵も感じさせない……オレが知っている彩が本物なのか、今、目の前にいる名前も知らない清楚な女性が本物なのか、知れば知るほど魅力的な女性だよ」
「クククッ……褒め言葉として受け取っとくね。でも、今の言葉は正確じゃない、昼間の清楚で上品な時は健志には会わないの……だから、ほら……」
白いシャツの裾を引き上げると、守るモノが何もなく、くすみの少ない股間が姿を表す。
「ねっ、健志の知っている彩のママでしょう……おはようのキスをしてくれないの??」
彩を見つめる健志の眩しそうな顔に自然と笑みが浮かび、そんな健志を見つめる彩の表情も屈託なく緩む。
「白いシャツがお日さまを反射して眩しいの??」
「嫌な女だな。キラキラした彩が眩しいんだよ。夜の灯りに慣れ過ぎたようだよ」
大きく開いた両手を彩に向けて伸ばすと、その間に入り込んで腿を跨いで首に両手を回し、
「昨日は気持ち良かったよ。知らない人に見られるかもしれないというドキドキ感も味わえたし、健志の吐き出した火傷するほど熱い満足の証も受けたし……今日は、お日さまが眩しい」
空を見上げる彩は目を眇め、いかにも眩しそうな表情になる。
「可愛いな。昼間の彩も魅力的な女性だろうと思うと残念だよ」
「うちの旦那をぶっちめて昼も夜も健志のモノにしたい??」
「そうだな、できる事ならそうしたいと思うよ」
「嬉しい、そう言ってくれるだけで彩は幸せ。本当にそんな事をするには全てを捨てる覚悟をしなきゃいけないけど……彩には無理」
「仕事??それとも、ご主人??」
「両方。今はピンチだけど好きで一緒になった人だし、健志も言ったでしょう。彩も主人以外の人とエッチすれば気持ちが分かるだろうし優しくなれるって。あれは彩を抱くための方便だったの??」
「そんな積りはなかったけど……改めて考えると何とも言えないな」
「そうなんだ……お腹が空いた。食べてもいい??」
牛乳だけのシンプルなオートミール、ベーコンと玉ねぎとキャベツのスープ、プレーンオムレツとソーセージ、ブロッコリーなどの温野菜がテーブルいっぱいに並んでいる。
どれもこれも湯気と匂いが食欲をそそり、たっぷりの牛乳を入れたミルクティが身体を芯から温めてくれる。
駅周辺の煌びやかな灯りは消えたものの健康的な賑わいは日曜の朝も絶えることがない。
「ねぇ、聞いてもいい??……夜の繁華街に人が集まれば集まるほど明るさが増し、それに伴って陰も濃くなるって言ったよね。影は悪なの??」
「どうしてそんな事を聞くのか分からないけどオレが思うのは、人間の欲望を満足させるのは困難だと思う。意識しないけど、何か満たされない思いが影となるんだと思うよ」
「うん、大体わかった。実はね明日、担当役員に新規プロジェクトの説明をしなければいけないんだけど、なんかヒントをもらったような気がする。それと、風俗って新しい業態って言うか次から次に法の網をくぐるような店が出来るでしょう、それはどう思うの??」
「欲望に限りがないってのが一番の理由で需要と供給って事だと思うけど、新規業態の店が出来て、その店が人気になれば、どうするか??」
「競合店や新規加入業者はどうするの??」
「これまで通りの店も当然あるだろうね。真似をする、その店を上回るサービスを考える……一番新しいって言うのは常に目標になるから、近い将来、一番じゃなくなる可能性が大きいだろうね。常に先を見て歩き続けることが必要だと思うよ」
食べる手を止めて健志の話を聞く彩は、何かが閃き頭の中が自分の意思を超えて駆け回るのを意識する。
「何か考えているようだけど、夜の街の妖しい蠢きが昼間の彩の仕事のヒントになるの??」
「まだ、はっきりと、まとまらないけど、イメージが掴めそうな気がする。昼も夜も対象は人間、ヒントはあると思うの」
すべての皿を空にしてミルクティを飲み干した二人は後片付けを終えて再びベランダに戻る。
椅子に座る健志の腿に座った彩はシャツのボタンを外して乳房に残る縄模様を愛おし気になぞる。
「誰かに見せてあげたい……夜の私は彩という女に変身して、こんな事をして楽しんいるんだよって」
「この白いムチムチとした身体はオレの許可なしで他人に見せちゃだめだよ。分かった??」
「彩は健志のモノなの??健志の女なの??……そんな事を言われて悦ぶ女だったんだ、彩は……ウフフッ、キスして」
唇を合わせて互いの身体を擦りながらも、彩が清楚な人妻に戻る時間が近付いているという現実がそれ以上の事を躊躇わせる。
「どうする、途中まで送ろうか??」
「駅まで歩いて電車に乗るから健志はここから見ていて……それより、縄やオモチャを他の人に使っちゃ嫌だよ」
「そんな事をするわけないよ。大きい紙袋に入れて彩が封印のサインをしとけばいいよ。オレが信用できないならね」
「クククッ、信用するけど、秘密めいていて楽しそう。それを採用」
坂道を駅に向かう彩を見送る健志は、
「あや~、浮気しちゃだめだぞ」と、他人を気にする様子もなく大声で叫んで手を振る。
彩は、笑みを浮かべる人や驚いた表情で彩と健志を見比べる人たちに軽く会釈し健志に手を振り足早に歩き始める。
駅に向かう時間と電車の時間、最寄り駅から自宅までの時間に彩から普段の自分に戻り、健志との記憶を封印して貞淑な妻に変身し、出張だと言って浮気する亭主を笑顔で迎えることが出来そうだと思う自分に恐れを抱く。