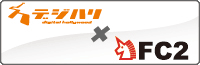彩―隠し事 322
転生 -27
仄かな灯りに包まれていた寝室はキャンドルが燃え尽きて真っ暗になり、視覚を奪われた彩と健志の感覚が鋭敏になってシーツが擦れる音にさえ卑猥な思いを募らせる。
愛する人に触れる舌や指先が命を帯びた性器のように感じられ、身体の隅々に向かって電気が走るような快感に襲われる。
彩は目の前で屹立する怒張を愛おしく思う。
夫の浮気に気付いてからも嫌いになれないものの二人の関係にほんの少し隙間ができ、周りの人が微風と感じるようなことも優子には吹きすさぶ寒風のように感じることがあった。
そんな時、性的に奔放なところがある学生時代からの親友に連れられて行ったSMショークラブをきっかけにして出会った健志と付き合うようになり、その負い目で浮気をする夫に寛大な態度で接することができ、相変わらず肌を接することはないが気持ちのつながりは元に戻りつつあるように感じている。
そんなきっかけを作ってくれた目の前の怒張が彩と接することで先走り汁を垂れ流し、欲望を露わにしているのだから嬉しく思わないはずがない。
「ウフフッ、可愛い。彩を悦ばせようとしてこんな大きくなっているの??それとも、彩なんかどうでもよくて自分だけ気持ち善くなりたいの??お返事は??」
ピシッ……いたいっ……真っ暗闇の中でもペニスの位置だけははっきり見えているかのように彩の指先は亀頭を弾き、健志は痛いと呻いて腰を捩って逃げようとする。
「あれっ、彩のことが嫌いなの??どっかに行っちゃった」
嫌いなのかと言われれば元の位置に戻るしかなく、腰を突き上げて彩の顔をつつく。
「逃げたんじゃない。悪いことをしていないのに弾くから避けただけで彩が嫌いになったんじゃないって言っているよ」
「ふ~ん、そうなんだ、指で弾いたことを怒っているんだ、オチンチンは自分で答えないで健志に答えさせた……いいよ、悪いのは痛くしちゃった彩だから、ゴメンね……」
独り言のように呟き終えた彩はパクリとペニスを口に含み、ジュルジュル音を立てて顔を上下し、絡ませた舌で先走り汁を舐め取り、竿の根元を摘まんで亀頭をベロッと舐めて鈴口を舌先でつつく。
「こんなに熱くておっきいオチンポもいいけど、彩のお口の中でムクムク起きてくれるのも好き」
「悪いな、彩の口に入れてもらうのを待ちきれなくて昂奮しちゃったよ。これはお詫びの代わりだよ」
再び割れ目を開いて小陰唇が作る溝を舐めると、クゥッ~と甘い吐息と共に膝立ちのシックスナインが崩れて股間が健志の顔にかぶさる。
苦しさを堪える健志は彩の腰に手を添えてわずかに隙間を作り、マン汁を溢れさせる泉に舌を捻じ込んで出し入れを繰り返す。
「アンッ、いやっ、気持ちいい……ウッウッ、健志のお鼻がクリに当たる、アンッ、いいの。彩もオチンチンをクチュクチュする」
膣口に侵入させた舌を出し入れすると自然と鼻頭がクリトリスをくすぐり、予期せぬ快感に彩は身悶えて顔に被さっていた股間から解放される。
ピチャピチャ、ヌチャヌチャ……ジュルジュルッ、ジュボジュボッ、ウッウグッ、クゥッ~……滲み出るマン汁を啜り、膣口からクリトリスに向かって下品な音を立てるのも構わず舌を躍らせ、彩は屹立する竿の根元を摘まんで滑りを舐め取り、喉を開いて奥深くまで咥え込んで静かに顔を揺する。
「たまんないよ、そんなことをされたら我慢できなくなる」
「えっ、ダメ、彩のアソコで満足してくれないと、イヤンッ」
こんな状況で漏らす、イヤンッと言う甘い声が健志の琴線を刺激して絶頂を迎えそうになる。
「ダメだよ、絶対にダメ。彩を残して逝かないで、一緒じゃなきゃダメ」
ペニスを吐き出した彩の声が暗闇で響く。
「クククッ、オレ独りじゃ敵いそうにないから援軍を呼ぶよ」
「えっ、うそでしょう??悠士さんを呼ぶの??イヤッ、今日はごっこでも夫婦でしょう、二人が好いの」
シックスナインで顔を跨ぐ彩の腰を左手で抱えた健志はヘッドボードに手を伸ばして指に触れるものを探り、笑みを浮かべる。
「悠士じゃないけど助っ人が来たよ、気持ち善くなれると思う」
暗闇で視覚が効かず、指先の感触で記憶の中の形状を思い出した健志は手の中のモノをマン汁が滴る泉に押し当てる。
「なに??指でも舌でもない、なんなの??何も見えないから怖い……変なモノを挿入されたくない」
「彩……オレは彩が大好きだよ。オレは大切なモノをぞんざいに扱わない、信じてくれるだろう??」
「うん、信じる」
彩はペニスの根元を握っていた手を離し、健志の顔を跨いだままの両脚をわずかに開いて突き出し、得体のしれない異物の挿入を待ち構える。
「ウッ、なに??……一緒に買ったバイブの感触の記憶はない。結構、気持ちいいかも、ハァハァッ……」
息を荒げ不安と共に妖しい期待を口にする彩はオマンコをヒクヒクさせて唇を噛み、蕩けそうになる快感で下半身が崩れ落ちそうになるのを堪えるために広げた両脚を踏ん張る。
「彩、スイッチを入れてほしいだろ??このままでもいいのか??」
挿入したオモチャを性感の発達した彩に快感を与えないようにゆっくり出し入れしながら意地の悪い言葉を口にする。
「動かしてください。エッチでスケベな彩を気持ち善くしてください、お願い、焦らされるのは嫌」
ドッドッ、ドッ……「えっ、なに??なに??何なの??バイブでしょう??」
慣れ親しんだバイブが振動で刺激するのとは違い、果てしなく打ち寄せる波のようにオマンコの入り口から奥に向かってズンズンッと経験したことのない刺激を与えられる。
彩の知るバイブのように出入りを繰り返すのではなく、いくつもの大玉が子宮に向かって膨れたり縮んだりしながら際限なく入ってくるような気がして怖いくらいの気持ち善さを与えてくれる。
「ウッウッ、クゥッ~…ダメッ、気持ちいい……}
喘ぎ声を漏らすまいとしても我慢することができず、ペニスを挿入されているような自然な柔らかさと十分な太さを持つ圧迫感は、このまま挿入を続けられると絶頂に誘われてしまいそうな気がして、
「いやっ、健志のオチンポが欲しい。彩はオチンポが好い」と、叫んでバイブを引き抜き、シックスナインの体勢から身体の向きを変えて騎乗位でつながろうとする。
仄かな灯りに包まれていた寝室はキャンドルが燃え尽きて真っ暗になり、視覚を奪われた彩と健志の感覚が鋭敏になってシーツが擦れる音にさえ卑猥な思いを募らせる。
愛する人に触れる舌や指先が命を帯びた性器のように感じられ、身体の隅々に向かって電気が走るような快感に襲われる。
彩は目の前で屹立する怒張を愛おしく思う。
夫の浮気に気付いてからも嫌いになれないものの二人の関係にほんの少し隙間ができ、周りの人が微風と感じるようなことも優子には吹きすさぶ寒風のように感じることがあった。
そんな時、性的に奔放なところがある学生時代からの親友に連れられて行ったSMショークラブをきっかけにして出会った健志と付き合うようになり、その負い目で浮気をする夫に寛大な態度で接することができ、相変わらず肌を接することはないが気持ちのつながりは元に戻りつつあるように感じている。
そんなきっかけを作ってくれた目の前の怒張が彩と接することで先走り汁を垂れ流し、欲望を露わにしているのだから嬉しく思わないはずがない。
「ウフフッ、可愛い。彩を悦ばせようとしてこんな大きくなっているの??それとも、彩なんかどうでもよくて自分だけ気持ち善くなりたいの??お返事は??」
ピシッ……いたいっ……真っ暗闇の中でもペニスの位置だけははっきり見えているかのように彩の指先は亀頭を弾き、健志は痛いと呻いて腰を捩って逃げようとする。
「あれっ、彩のことが嫌いなの??どっかに行っちゃった」
嫌いなのかと言われれば元の位置に戻るしかなく、腰を突き上げて彩の顔をつつく。
「逃げたんじゃない。悪いことをしていないのに弾くから避けただけで彩が嫌いになったんじゃないって言っているよ」
「ふ~ん、そうなんだ、指で弾いたことを怒っているんだ、オチンチンは自分で答えないで健志に答えさせた……いいよ、悪いのは痛くしちゃった彩だから、ゴメンね……」
独り言のように呟き終えた彩はパクリとペニスを口に含み、ジュルジュル音を立てて顔を上下し、絡ませた舌で先走り汁を舐め取り、竿の根元を摘まんで亀頭をベロッと舐めて鈴口を舌先でつつく。
「こんなに熱くておっきいオチンポもいいけど、彩のお口の中でムクムク起きてくれるのも好き」
「悪いな、彩の口に入れてもらうのを待ちきれなくて昂奮しちゃったよ。これはお詫びの代わりだよ」
再び割れ目を開いて小陰唇が作る溝を舐めると、クゥッ~と甘い吐息と共に膝立ちのシックスナインが崩れて股間が健志の顔にかぶさる。
苦しさを堪える健志は彩の腰に手を添えてわずかに隙間を作り、マン汁を溢れさせる泉に舌を捻じ込んで出し入れを繰り返す。
「アンッ、いやっ、気持ちいい……ウッウッ、健志のお鼻がクリに当たる、アンッ、いいの。彩もオチンチンをクチュクチュする」
膣口に侵入させた舌を出し入れすると自然と鼻頭がクリトリスをくすぐり、予期せぬ快感に彩は身悶えて顔に被さっていた股間から解放される。
ピチャピチャ、ヌチャヌチャ……ジュルジュルッ、ジュボジュボッ、ウッウグッ、クゥッ~……滲み出るマン汁を啜り、膣口からクリトリスに向かって下品な音を立てるのも構わず舌を躍らせ、彩は屹立する竿の根元を摘まんで滑りを舐め取り、喉を開いて奥深くまで咥え込んで静かに顔を揺する。
「たまんないよ、そんなことをされたら我慢できなくなる」
「えっ、ダメ、彩のアソコで満足してくれないと、イヤンッ」
こんな状況で漏らす、イヤンッと言う甘い声が健志の琴線を刺激して絶頂を迎えそうになる。
「ダメだよ、絶対にダメ。彩を残して逝かないで、一緒じゃなきゃダメ」
ペニスを吐き出した彩の声が暗闇で響く。
「クククッ、オレ独りじゃ敵いそうにないから援軍を呼ぶよ」
「えっ、うそでしょう??悠士さんを呼ぶの??イヤッ、今日はごっこでも夫婦でしょう、二人が好いの」
シックスナインで顔を跨ぐ彩の腰を左手で抱えた健志はヘッドボードに手を伸ばして指に触れるものを探り、笑みを浮かべる。
「悠士じゃないけど助っ人が来たよ、気持ち善くなれると思う」
暗闇で視覚が効かず、指先の感触で記憶の中の形状を思い出した健志は手の中のモノをマン汁が滴る泉に押し当てる。
「なに??指でも舌でもない、なんなの??何も見えないから怖い……変なモノを挿入されたくない」
「彩……オレは彩が大好きだよ。オレは大切なモノをぞんざいに扱わない、信じてくれるだろう??」
「うん、信じる」
彩はペニスの根元を握っていた手を離し、健志の顔を跨いだままの両脚をわずかに開いて突き出し、得体のしれない異物の挿入を待ち構える。
「ウッ、なに??……一緒に買ったバイブの感触の記憶はない。結構、気持ちいいかも、ハァハァッ……」
息を荒げ不安と共に妖しい期待を口にする彩はオマンコをヒクヒクさせて唇を噛み、蕩けそうになる快感で下半身が崩れ落ちそうになるのを堪えるために広げた両脚を踏ん張る。
「彩、スイッチを入れてほしいだろ??このままでもいいのか??」
挿入したオモチャを性感の発達した彩に快感を与えないようにゆっくり出し入れしながら意地の悪い言葉を口にする。
「動かしてください。エッチでスケベな彩を気持ち善くしてください、お願い、焦らされるのは嫌」
ドッドッ、ドッ……「えっ、なに??なに??何なの??バイブでしょう??」
慣れ親しんだバイブが振動で刺激するのとは違い、果てしなく打ち寄せる波のようにオマンコの入り口から奥に向かってズンズンッと経験したことのない刺激を与えられる。
彩の知るバイブのように出入りを繰り返すのではなく、いくつもの大玉が子宮に向かって膨れたり縮んだりしながら際限なく入ってくるような気がして怖いくらいの気持ち善さを与えてくれる。
「ウッウッ、クゥッ~…ダメッ、気持ちいい……}
喘ぎ声を漏らすまいとしても我慢することができず、ペニスを挿入されているような自然な柔らかさと十分な太さを持つ圧迫感は、このまま挿入を続けられると絶頂に誘われてしまいそうな気がして、
「いやっ、健志のオチンポが欲しい。彩はオチンポが好い」と、叫んでバイブを引き抜き、シックスナインの体勢から身体の向きを変えて騎乗位でつながろうとする。