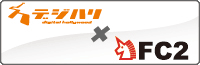おとぎ話
膝枕-1
「おはよう・・・まだ、夜中だけどね」
「うん??・・・寝ちゃったのか、ごめんね」
横になったまま視線を巡らすとウィスキーやリキュールのボトルが並ぶバックバーを照らす照明が眩しい。
オーナーでありオレを覗き込むママともう一人、女性二人でやっている店であり、酒の種類や銘柄が驚くほど揃っているわけではないが、シンプルでモダンなデザインのバックバーはいつ見てもきれいに整理されていて気持ちが好い。
毎日ボトルを拭いているのを知っているし、常にラベルが正面を向くように、しかも整然と並べられているのが心地良い。
ママはオレを見つめ髪を撫で続ける。
「気持ち良さそうに寝ていたわよ」
「そうか、ごめんね。片付けるのに邪魔にならなかった??」
「う~ん・・・このシートは、まだ拭いてない」
「ごめん、どれくらい寝ていた??」
「一時間くらいかな・・・寝顔が可愛かったよ。心配な事が一つあったけどね・・・」
「心配な事??・・・何だろう??迷惑かけなかったかな??」
「ウフフッ、そうじゃない。寝言で知らない名前を呼んだらどうしようと思って・・・」
「バカッ、本当はそんな心配なんかしてないだろう??・・・」
「名前呼び違えては叱られて・・・って、詩の歌があったよね・・・」
「クククッ・・・なんか気持ち良いな。膝枕って温かくて柔らくて・・・いつまでもこうしていたいよ」
「いいよ、私で良ければ、いつでもしてあげる。
手を伸ばして腿の感触を確かめようとしたオレは違和感で身体を起こす。
身に着けていたはずのスカートはなく、赤いショーツとストッキング姿で膝枕をしてくれていたようだ。
「その恰好、オレは寝ながら失礼な事をしちゃったのかな??」
「変な事をしていたら責任取ってくれる??」
「そりゃ・・・オレも男の子だから・・・」
「フフフッ・・・忘れたの??その言葉は失礼だよ」
そうだ思い出した。あれは先週の事だった・・・・
「それでは、お先に失礼します。柏木さん、ママをよろしく・・・」
後片付けを終え、ママとオレを残してアキちゃんは帰った。
店に残ったのはママとオレの二人。アキちゃんの目にどう映っているか分からないが、二人の間には今のところ何もない。
しようかは失礼だし、やっても良いと聞くのはもっと無礼だろう。
オレはママが好きだし、ママもオレに好意を持ってくれていると思っている。
何事にもきっかけがある。肌を合わせる機会はあったはずなのに、好きな女性に優柔不断になる悪癖でズルズルと今に至ってしまった。
「もう少し飲む??」
バランタイン30年を取り出したママは言う。
スコッチウィスキーの最高峰といわれるバランタイン30年。
30年の長きにわたり熟成されたウィスキー、熟成の過程で天使の隠れ飲みも相当の量になるという。
飲んでみたい・・・オレに断る理由はない。
タンブラーとミネラルウォーター、アイスバスケットとバランタインをカウンターに置いたママはオレの後ろに立つ。
「どっちに座ればいい??」
「左・・・」
悪戯を待つ女はオレの左側に座らせる。利き手である右手を自由に動かすにはその方が良い。
オレは二つのタンブラーを引き寄せて一つには氷を入れて軽くステアし、グラスを冷やす。
「薄くして・・・」
両方のグラスにバランタインを入れてミネラルウォーターを注ぐ。
氷を入れた水割りをママの前に置き、氷の入ってないトゥワイスアップを手に取ったオレは深みのある琥珀色を目で味わい、ママと視線を合わせながら目の高さで捧げ持ち、バランタインにと言って乾杯する。
ウィスキーの味を的確に表現するほど味が分かるわけではないが、口に含んで鼻に抜けてゆく香りを楽しむ。30年の年を刻んだバランタインは尖ったところがなく力強さのある芳醇な味は確かに美味いと感じる。
「美味しい??」
「うん、オレでも美味いと思う・・・」
絶妙な距離、ママとオレの間には絶妙な距離がある。
ママが水割りグラスに手を伸ばすとオレの左手に微かに触れ、オレがママの方に身体を向けると左膝がママの右足に軽く触れる。
近すぎず、遠からず・・・微妙な距離・・・好意を持つ相手だけに今更ながら手を伸ばすには遠く、心をつなげるには近い絶妙な距離を感じる。
トゥワイスアップで香りと深みのある味を堪能したオレは氷を入れた水割りを1杯、また1杯と飲み干す。
肌を重ねた事のない二人にとって近すぎるこの距離では話題も途切れてしまい、気が付いた時はこの場所、同じ格好でママの膝を枕に寝ていた。
目覚めたオレの眼ヤニを小指で拭いながらママは、
「あのね、スカートが皺になるんだけど・・」
「それは悪いことをしたね、この次はスカートを脱いで膝枕してくれる??」
「そうね、それがいいわね。今度はそうする・・」
カウンターからどうやってオレを運んだのかとは口にはしなかった。
「おはよう・・・まだ、夜中だけどね」
「うん??・・・寝ちゃったのか、ごめんね」
横になったまま視線を巡らすとウィスキーやリキュールのボトルが並ぶバックバーを照らす照明が眩しい。
オーナーでありオレを覗き込むママともう一人、女性二人でやっている店であり、酒の種類や銘柄が驚くほど揃っているわけではないが、シンプルでモダンなデザインのバックバーはいつ見てもきれいに整理されていて気持ちが好い。
毎日ボトルを拭いているのを知っているし、常にラベルが正面を向くように、しかも整然と並べられているのが心地良い。
ママはオレを見つめ髪を撫で続ける。
「気持ち良さそうに寝ていたわよ」
「そうか、ごめんね。片付けるのに邪魔にならなかった??」
「う~ん・・・このシートは、まだ拭いてない」
「ごめん、どれくらい寝ていた??」
「一時間くらいかな・・・寝顔が可愛かったよ。心配な事が一つあったけどね・・・」
「心配な事??・・・何だろう??迷惑かけなかったかな??」
「ウフフッ、そうじゃない。寝言で知らない名前を呼んだらどうしようと思って・・・」
「バカッ、本当はそんな心配なんかしてないだろう??・・・」
「名前呼び違えては叱られて・・・って、詩の歌があったよね・・・」
「クククッ・・・なんか気持ち良いな。膝枕って温かくて柔らくて・・・いつまでもこうしていたいよ」
「いいよ、私で良ければ、いつでもしてあげる。
手を伸ばして腿の感触を確かめようとしたオレは違和感で身体を起こす。
身に着けていたはずのスカートはなく、赤いショーツとストッキング姿で膝枕をしてくれていたようだ。
「その恰好、オレは寝ながら失礼な事をしちゃったのかな??」
「変な事をしていたら責任取ってくれる??」
「そりゃ・・・オレも男の子だから・・・」
「フフフッ・・・忘れたの??その言葉は失礼だよ」
そうだ思い出した。あれは先週の事だった・・・・
「それでは、お先に失礼します。柏木さん、ママをよろしく・・・」
後片付けを終え、ママとオレを残してアキちゃんは帰った。
店に残ったのはママとオレの二人。アキちゃんの目にどう映っているか分からないが、二人の間には今のところ何もない。
しようかは失礼だし、やっても良いと聞くのはもっと無礼だろう。
オレはママが好きだし、ママもオレに好意を持ってくれていると思っている。
何事にもきっかけがある。肌を合わせる機会はあったはずなのに、好きな女性に優柔不断になる悪癖でズルズルと今に至ってしまった。
「もう少し飲む??」
バランタイン30年を取り出したママは言う。
スコッチウィスキーの最高峰といわれるバランタイン30年。
30年の長きにわたり熟成されたウィスキー、熟成の過程で天使の隠れ飲みも相当の量になるという。
飲んでみたい・・・オレに断る理由はない。
タンブラーとミネラルウォーター、アイスバスケットとバランタインをカウンターに置いたママはオレの後ろに立つ。
「どっちに座ればいい??」
「左・・・」
悪戯を待つ女はオレの左側に座らせる。利き手である右手を自由に動かすにはその方が良い。
オレは二つのタンブラーを引き寄せて一つには氷を入れて軽くステアし、グラスを冷やす。
「薄くして・・・」
両方のグラスにバランタインを入れてミネラルウォーターを注ぐ。
氷を入れた水割りをママの前に置き、氷の入ってないトゥワイスアップを手に取ったオレは深みのある琥珀色を目で味わい、ママと視線を合わせながら目の高さで捧げ持ち、バランタインにと言って乾杯する。
ウィスキーの味を的確に表現するほど味が分かるわけではないが、口に含んで鼻に抜けてゆく香りを楽しむ。30年の年を刻んだバランタインは尖ったところがなく力強さのある芳醇な味は確かに美味いと感じる。
「美味しい??」
「うん、オレでも美味いと思う・・・」
絶妙な距離、ママとオレの間には絶妙な距離がある。
ママが水割りグラスに手を伸ばすとオレの左手に微かに触れ、オレがママの方に身体を向けると左膝がママの右足に軽く触れる。
近すぎず、遠からず・・・微妙な距離・・・好意を持つ相手だけに今更ながら手を伸ばすには遠く、心をつなげるには近い絶妙な距離を感じる。
トゥワイスアップで香りと深みのある味を堪能したオレは氷を入れた水割りを1杯、また1杯と飲み干す。
肌を重ねた事のない二人にとって近すぎるこの距離では話題も途切れてしまい、気が付いた時はこの場所、同じ格好でママの膝を枕に寝ていた。
目覚めたオレの眼ヤニを小指で拭いながらママは、
「あのね、スカートが皺になるんだけど・・」
「それは悪いことをしたね、この次はスカートを脱いで膝枕してくれる??」
「そうね、それがいいわね。今度はそうする・・」
カウンターからどうやってオレを運んだのかとは口にはしなかった。